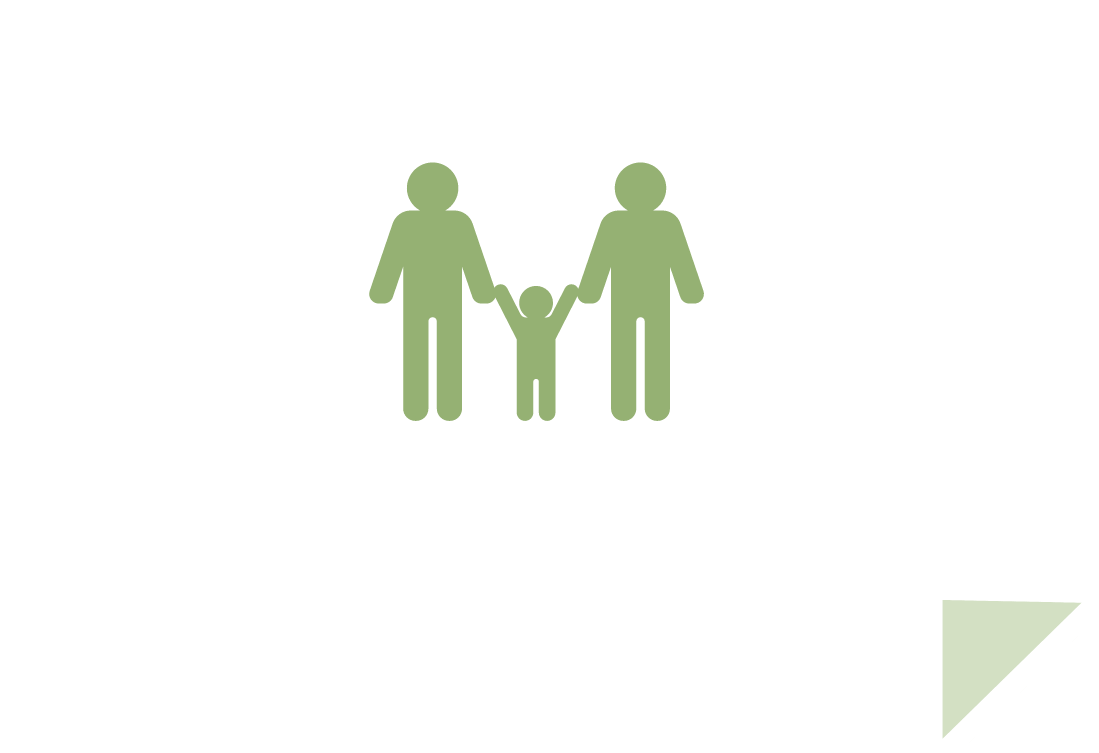注文住宅の最大の魅力は、こだわりや希望が実現できることです。ただし、あらかじめ予算を決めておかないと、建築費用は際限なく高くなってしまいます。そこで今回は、注文住宅の適正な予算の考え方について解説します。
まず押さえよう!注文住宅の平均購入価格

住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」によると、注文住宅(※)の所要資金の全国平均は3,861万円、土地付注文住宅(※)では4,903万円です。所要資金※は、全体として上昇傾向が続いており、2023年度は、全ての融資区分で前年度から上昇した。ちなみに、地域別の平均所要所得は以下のとおりです。
※注文住宅:建物代のみ融資を受けた世帯
※土地付き注文住宅:土地代と建物代の両方の融資を受けた世帯
| 注文住宅 | 土地付注文住宅 | |
| 全国平均 | 3,861万円 | 4,903万円 |
| 首都圏 | 4,190万円 | 5,679万円 |
| 近畿圏 | 4,142万円 | 5,266万円 |
| 東海圏 | 3,893万円 | 4,810万円 |
| その他地域 | 3,623万円 | 4,299万円 |
2021年から深刻な木材不足による世界的な木材価格の高騰、いわゆる「ウッドショック」が起こっています。ウッドショックが発生した要因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で「巣ごもり需要」が高まり、アメリカや中国で住宅購入・リフォームが急増したためといわれています。約6割を輸入木材に頼る日本でも、今後しばらくは木造住宅の価格高騰が続くかもしれません。
※注文住宅の平均購入価格に関する情報は、2024年4月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
頭金は3割近くも
住宅購入における頭金は、一般的には購入価格の1〜2割とされています。注文住宅ではどうでしょうか。国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、新築注文住宅(土地含む)の全国平均購入金額は5,811万円、頭金平均金額は1,685万円、頭金の割合は29.0%です。注文住宅においては、頭金は多めに入れる傾向があるようです。
【参考URL】
※注文住宅の平均購入価格に関する情報は、2024年4月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
注文住宅の購入予算は?目安となる2つの基準も紹介

住宅購入の予算は「自己資金+住宅ローンの借入可能額」です。住宅ローンの借入可能額の概算は「年収倍率」で、そもそも住宅ローンが組めるのかは「返済負担率(返済比率)」で確認できます。それぞれの基準を確認してみましょう。
年収倍率
年収倍率とは、「希望する住宅購入価額が世帯年収の何倍に相当するか」を比率で表したものです。一般的に、年収倍率は5〜6倍が望ましいとされています。たとえば、日本人の平均年収461万円(2020年時点)で考えると、2,305~2,766万円の住宅が適当ということになります。
ただし近年は、資材の価格が高騰しているという背景もあり、注文住宅の価格ならびに年収倍率は上昇傾向です。先ほど参考にした住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」によると、年収倍率の全国平均は注文住宅で6.9倍、土地付注文住宅で7.7倍となっています。年収461万円で計算すると、注文住宅は約3,181万円、土地付注文住宅は約3,550万円が購入可能な住宅価格の目安ということです。
この年収倍率は、融資の判断基準の目安としても使用されます。金融機関によっては年収の8倍以上の貸し付けをするところもありますが、無理な借り入れは避けましょう。年収に対する借入金額があまりに高すぎると返済そのものが厳しくなり、家計を圧迫する恐れがあります。
参照:「国税庁 平均給与」
※注文住宅の購入予算に関する情報は、2024年4月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
返済負担率(返済比率)
返済負担率(返済比率)とは、「世帯年収に占める年間返済額の割合」を表すもので、融資審査の際に金融機関が重視する数値の1つです。返済負担率が35%を超えた場合、ほとんどの金融機関では住宅ローンの申し込みを受け付けてくれません。
返済負担率を求めるには「年間総返済額÷年収×100%」で計算します。返済額には自動車ローンやカードローンなどの返済も含まれます。年収430万円で住宅ローンの年間総返済額を100万円とすると、返済負担率は約23%です。これに他のローンが加わると、返済負担率は30%を超える可能性もあるでしょう。
ちなみに、家計を圧迫しない返済負担率は20〜25%ほどとされています。30%を超えると家計状況によっては返済が厳しくなることが予想されるため、慎重に検討してください。
注文住宅の費用内訳について

次に、注文住宅に必要な「土地代」「建物代」「諸費用」を確認していきましょう。それぞれの目安や注意点について解説します。
土地代
土地とセットで販売されている建売住宅と違い、注文住宅を建てる場合はまず自分たちで土地を準備しなくてはなりません。もともと土地を所有している場合を除き、土地の購入費用が必要です。
土地の価格は、立地によって異なります。都市部よりも地方のほうが安い傾向にありますし、駅から遠くなるほど価格が下がるのが一般的です。土地の形状や方角なども価格に反映されます。たとえば、形が整っていない不整形地や西向き・北向きの土地など、需要が少ない土地は比較的安く売り出されます。
なお、地盤が弱い土地には地盤改良工事が必要です。工法や土地の面積、建物の重量や建築面積などで異なりますが、50~200万円ほどが工事費の目安となります。
建物代
次の2つの費用の合計が建物代になります。
・本体工事費用:仮設工事、基礎工事、木工事、外装、内装、住宅設備など
・付帯工事費用:外構工事、電気・ガス・給排水の引き込み工事など
一般的には、建物代の70~75%ほどが本体工事、20~25%ほどが付帯工事の目安と考えます。ただし、付帯工事は立地や敷地条件によって変動することがあります。たとえば、既存の建物がある場合は解体工事が発生しますし、下水道が開通していない地域では浄化槽の設置工事が必要です。地盤改良工事も付帯工事に含まれます。
住宅購入にかかる諸費用
注文住宅購入にかかる諸費用には、次のようなものが挙げられます。
・設計費用
・建築確認申請費用
・工事請負契約書費用
・建物表示登記費用
・所有権保存登記費用
・住宅ローン関連費用
・水道加入料
・地鎮祭・上棟式費用
諸費用は土地代+建物代の10〜20%前後を目安にすると良いでしょう。たとえば、購入価格が3,000万円の場合、諸費用として300万〜600万円ほどがかかる計算です。
予算オーバーしてしまった!?そんなときどうする?
プラン作成の段階で予算オーバーしてしまった場合は、次の点を見直してみてください。
・家の形
・間取り
・設備のグレード
家の形は、シンプルなほどコストダウンにつながります。凹凸が多い家は施工が複雑になり、基礎や屋根にかかる費用も膨らみがちです。延べ床面積が広くなるほど費用がかかるので、間取りにムダがないかも見直してみましょう。
浴室やキッチンなどの住宅設備や内装材のグレードを見直すのも、コストダウンに効果的です。「これだけは譲れない」というものを決めて、場合によっては、屋根材や外壁材、玄関ドアなども見直してみてください。
ただし家の安全性や性能にかかわる部分は、予算を削るべきではありません。基礎や柱・梁などの構造材は耐震性に影響しますし、断熱材や窓は家の断熱性・気密性に影響します。設計士や施工会社と相談しながら、安全で住み心地の良い家をつくっていきましょう。
注文住宅の適正な予算を把握したいなら、実績多数のトヨタホームに相談してみよう
注文住宅には相場がありません。そのため、予算を立てるにしても悩むことが多くなります。家族にとってどのくらいが適正な予算なのか分からないという方は、注文住宅をはじめ実績豊富なトヨタホームの展示場で相談してみてはいかがでしょうか。注文住宅づくりの経験豊富なスタッフが、あなたの家づくりをサポートします。
【全国のトヨタホーム展示場を探す】
https://www.toyotahome.co.jp/s/tenjijo/?ad_cd=hometag
【カタログ請求はこちら】
https://www.toyotahome.co.jp/s/catalog/?ad_cd=hometag
▼関連する記事
注文住宅とは?建売住宅との違いは?価格の相場や流れも分かりやすく解説
最大で100万円!今話題の「こどもみらい住宅支援事業」とは?分かりやすく解説!
失敗しない注文住宅の間取り!7つのポイントと決める手順のコツも紹介
注文住宅の坪単価ってどうやって計算するの?平均相場も合わせてリサーチ!
ハウスメーカーの選び方!4つのポイントを押さえるだけでぴったりの会社がわかる!
こだわるなら注文住宅?スピード重視なら建売住宅?両者の違いを分かりやすく解説!
注文住宅の相場は約3,861万円!?建築費用の内訳や建築コストを抑える方法も伝授
注文住宅の予算の決め方!適正な借入金額を把握して立ててみよう
注文住宅は広いリビングが人気!その理由とは?間取り決めの参考にしよう
【新築注文住宅】家づくりの流れを4つのステップで確認!期間の目安も
【注文住宅】完成するまでどのくらい期間がかかる?流れも合わせて解説
注文住宅でこだわりのキッチンを!後悔しない選び方を詳しく解説
注文住宅を建てる際の諸費用はどのくらいかかる?内訳や相場も解説
【新築注文住宅】内装デザインの決め方は?おしゃれになるコツを実例で解説
注文住宅の費用内訳を知りたい!総費用の平均額や各費用の目安も押さえておこう
失敗しない注文住宅づくり!よくある後悔事例からやっておくべきポイントを紹介
【注文住宅】間取りの決め方、6つの手順!人気の間取りアイデアも紹介