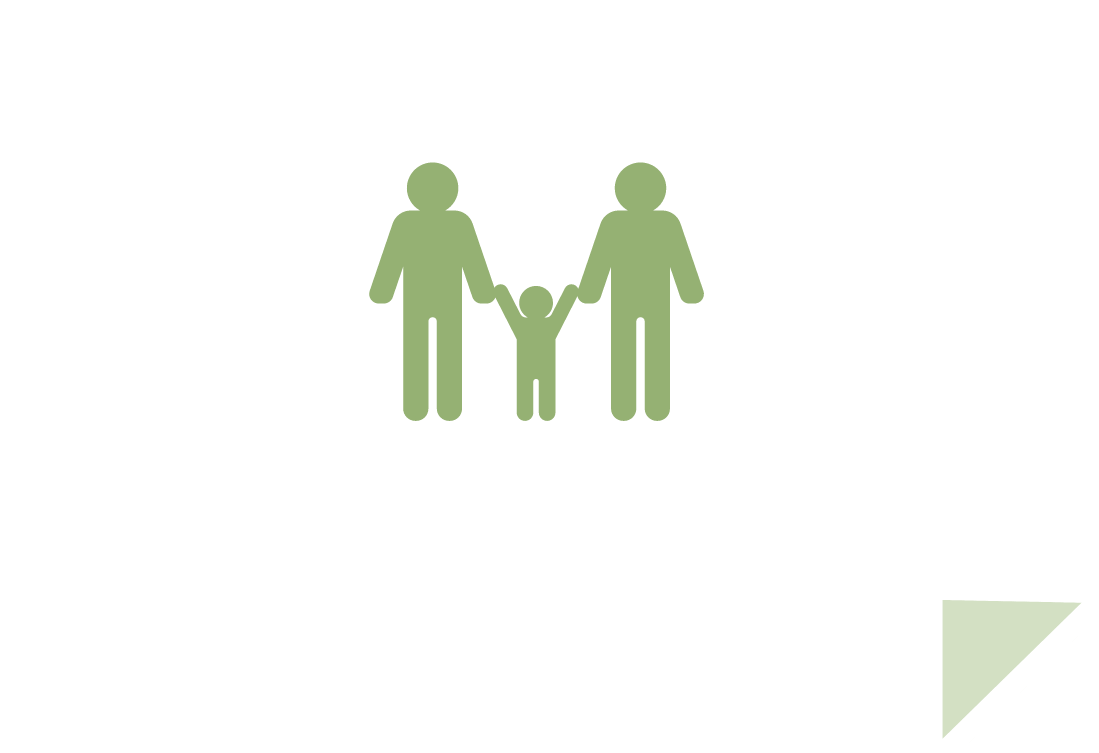注文住宅に限らず、マイホームや土地購入時には「諸費用」が発生します。諸費用は手数料や住宅ローンの保証料なども含まれており、トータルで数百万円になることもあります。特に注文住宅は建築費の総額が高くなりやすいため、「諸費用はどのくらいかかるのだろう」と不安になる人もいるでしょう。
そこでこの記事では、注文住宅の購入時に発生する諸費用の内訳をはじめ、相場について解説します。相場感をつかんで、事前に資金計画をしっかり立てておきましょう。
注文住宅の諸費用はどのくらいかかる?

諸費用とは、注文住宅の建築費用以外にかかる費用のことです。例えば、土地購入時の仲介手数料や登記費用などがそれに当たります。諸費用が発生するタイミングは大きく分けて「住宅購入時」と「住宅ローン契約時」の2回です。新築か中古か、戸建てかマンションかなど物件の種類によってもかかる費用は異なります。まずは大まかな諸費用の費用感を把握してみましょう。
注文住宅の場合、住居を取得する際にかかる費用総額の10%程度を占めるといわれています。単純に計算すると、例えば総額が2,000万円なら200万円、4,000万円なら400万円になります。できればこの諸費用は、住宅ローンの借りすぎを防ぐため現金での支払がよいといわれるため、事前に用意しておく必要があります。では、次にどのような諸費用が発生するのか項目について見ていきましょう。
※注文住宅の諸費用に関する情報は、2024年4月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
注文住宅の購入時にはどのような諸費用が発生する?
注文住宅では、具体的に以下の諸費用が発生します。
・仲介手数料
・不動産売買契約書の収入印紙代
・工事請負契約書の収入印紙代
・所有権保存・移転登記の費用
・建物表題登記の費用
・火災・地震保険料
・不動産取得税
・金銭消費貸借契約書の収入印紙代
・融資手数料
・ローン保証料
・抵当権設定登記の費用
上記の費用はあくまでも、購入時や住宅ローンの契約時に発生する諸費用です。この諸費用とは別に毎年、固定資産税や都市計画税などの税金がかかることも忘れないようにしましょう。それぞれの費用について詳しく解説します。
住宅購入時に発生する諸費用

最初に「住宅購入時」に発生する諸費用から解説します。
仲介手数料
仲介手数料とは、注文住宅を建てる土地を購入した場合、仲介してくれた不動産業者に対して支払う手数料のことです。ただし売主から直接、土地を購入した場合は、仲介手数料はかかりません。
また仲介手数料は法律で上限が定められていて、その上限額は売買価格によって異なります。上限額は以下の通りです。ちなみに土地の売買のみの仲介手数料には消費税はかかりません。
200万円まで:取引額の5%
200万円超え400万円まで:取引額の4%
400万円超え:取引額の3%
売買価格が400万円を超える場合は、速算式「(物件価格×3%+6万円)+消費税」を用いて計算します。上限の目安を知りたい人向けに早見表にまとめたので、参考にしてください。
| 売買価格 | 仲介手数料(税込み) |
| 1,000,000円 | 55,000円 |
| 2,000,000円 | 110,000円 |
| 3,000,000円 | 154,000円 |
| 4,000,000円 | 198,000円 |
| 5,000,000円 | 231,000円 |
| 6,000,000円 | 264,000円 |
| 7,000,000円 | 297,000円 |
| 8,000,000円 | 330,000円 |
| 9,000,000円 | 363,000円 |
| 10,000,000円 | 396,000円 |
| 20,000,000円 | 726,000円 |
| 30,000,000円 | 1,056,000円 |
| 40,000,000円 | 1,386,000円 |
| 50,000,000円 | 1,716,000円 |
| 60,000,000円 | 2,046,000円 |
| 70,000,000円 | 2,376,000円 |
| 80,000,000円 | 2,706,000円 |
| 90,000,000円 | 3,036,000円 |
| 100,000,000円 | 3,366,000円 |
※仲介手数料は消費税(10%)込みで計算
不動産売買契約書の収入印紙代
収入印紙とは、契約書などの文書を作成した際に、国に対して収める税金のことです。納める税額は契約書に記されている金額によって異なります。例えば、4,000万円の土地を購入するなら、「1,000万円を超え5,000万円以下のもの」となり税額は2万円です。ただし、2027年3月31日までに作成された契約書については、軽減措置が適用されて、税額は1万円となります。
工事請負契約書の収入印紙代
注文住宅の場合は、工事を依頼した施工会社との間で工事請負契約書の締結が必要となり、その契約書にも収入印紙が必要です。不動産売買契約書と同様、納める税額は契約書に記されている金額です。「1,000万円を超え5,000万円以下」であれば税額は2万円ですが、こちらも不動産売買契約書同様、軽減措置が適用されており、2027年3月31日までに作成された契約書については、税額は1万円となります。
所有権保存・所有権移転登記の費用
建物を新築した際は、その建物に対して自分の所有権を明示するために所有権保存登記、また土地の所有権移転登記を行う必要があります。その登記の際には、「登録免許税」を支払わなければなりません。
登録免許税額は「不動産の価額」✕「税率」で求められます。不動産の価額は、固定資産税評価額ですが、新築などで固定資産税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価格となります。
例えば、建物の固定資産評価額が2,000万円で、税率0.4%の登録免許税額は8万円です。土地の所有権移転登記については2026年3月31日まで本則2.0%が1.5%の軽減措置があります。登記手続きを専門家の司法書士に依頼すると、2万〜10万円ほどの報酬が別途必要となることも覚えておきましょう。
建物表題登記の費用
建物表題登記とは、まだ登記されていない建物について新規で行う登記のことです。注文住宅の場合、建物を新築したら最初に行わなければならない登記です。建売住宅や新築マンションの場合は、売主が行っているケースが大半で買主は原則行いません。ただし、建物表題登記では登録免許税はかかりません。しかし、専門家である土地家屋調査士に依頼するなら、その報酬として10万円程度を支払う必要があります。
火災・地震保険料
火災保険の保険料は築年数や住宅の構造、住宅の所在地といった条件によって大きく異なります。火災保険の保険料は各保険会社や補償内容によって多少の違いはあるものの、火災に加えて、風災や水災、盗難などの補償をカバーしたい場合は、鉄骨造・T構造(東京都、保険期間5年、新築、建物価格1,500万円)で年間保険料は約25,000円~26,000円です。
※時期によって、年間保険料は変動いたしますので、ご了承下さい。
参照:i保険 火災保険料シミュレーション(戸建て)
https://www.kasai-hoken.info/search/home/st1/s_1/8/ei1/hi1500/z/pr13/?te=34&gi=0&ab=1
地震保険は単独では加入はできないため、火災保険とセットで加入しましょう。地震保険の保険料は住んでいる地域と建物構造で決まります。例えば鉄骨造・T構造の場合(東京都、保険期間5年、新築、建物価格1,500万円)、年間保険料は火災保険料に12,380円~20,630円プラスされる形になります。
参照:あいおいニッセイ同和損保 地震保険保険料試算
https://www.aioinissaydowa.co.jp/personal/product/tough/house/calculate.aspx
ちなみに現在、火災保険は最長の10年契約が廃止されたため、最長で5年契約しかできません。また、耐火性や、耐震性の観点から、鉄筋コンクリート造の住宅の方が木造住宅の方が保険料は安くなります。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋の建築などで不動産を取得した際に、取得した人に対して課税される税金のことです。これは、取得したときに1回だけ支払うものです。
不動産取得税を求める計算式は「不動産の固定資産税評価額×税率4%」。
固定資産税評価額が2,000万円の建物なら、80万円が不動産取得税となります。
ちなみに、現在建物と土地それぞれに軽減税率として3%が適用されます。また、条件を満たせば新築住宅や土地に関する特例による軽減もあります。
※住宅購入時に発生する費用に関する情報は、2024年4月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
住宅ローンの契約時に発生する諸費用

続いて、住宅ローンの契約時にかかる諸費用について解説します。
金銭消費貸借契約書の収入印紙代
金銭消費賃借契約書とは、金銭を消費貸借の対象とする契約のことで、借り入れを行う金融機関と締結する契約書です。不動産売買契約書や建設工事請負契約書同様、収入印紙代が必要となります。ただし、こちらに関して軽減措置はありません。例えば、契約書に2,000万円の金額が記されているなら、「1,000万円を超え5,000万円以下のもの」になり、納める税額は2万円となります。
融資手数料
融資手数料とは、借り入れする金融機関に支払う住宅ローンの費用のことです。一般的に、融資手数料は約5万円が目安です。ネット銀行など低金利な住宅ローンでは、融資額に対して2.2%などの定率に設定されていることもあるので、手数料を抑えたい場合は融資手数料の安い金融機関を選ぶと良いでしょう。
ローン保証料
ローン保証料とは、保証人を保証会社に依頼する際にかかる費用のことです。金利に含まれていたり、金融機関が負担したりすることもあり、別途支払わなくてもよい場合もあります。別途支払う場合は、金額1,000万円に対し返済期間35年では20万円がおよその金額といわれています。例えば、3,000万円の借り入れなら、約60万円を見積もっておくとよいでしょう。
抵当権設定登記の費用
抵当権とは、いわゆる「担保」と呼ばれるものです。借り入れの際、返済不能に陥った際に備えて、金融機関が土地や建物に抵当権を設定するように求めてきます。その際には登録免許税の支払いが必要となります。
登録免許税を求める計算式は「住宅ローンの借入金額×0.4%」です。3,000万円の借り入れには、12万円の登録免許税がかかる計算になります。ただし、一定条件を満たすと、2026年3月31日まで税率が0.1%になる特例措置の対象になります。さらに、登記を専門家の司法書士に依頼する場合、報酬として別途5万~10万円ほどがかかるのでこの費用についても考慮しておきましょう。
※住宅ローン契約時に発生する諸費用に関する情報は、2024年4月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
注文住宅を建てるなら、税金の優遇措置を活用して諸費用を抑えよう
注文住宅の場合、建築費の総額が高いため、それに比例して諸費用も高くなりやすい傾向があります。総額の10%を目安に資金計画を立てておくと安心です。国による税金の優遇措置も用意されているため、優遇措置を大いに活用することで、かなり税金負担が軽減されるので事前に調べておきましょう。
さらに、注文住宅を多く手掛けているハウスメーカーに相談しながら進めると資金計画もよりスムーズに進められます。トヨタホームはお客様の要望や状況に合ったアドバイスで、一生に一度の家づくりをサポートしています。資金計画でもお悩みがある方をはじめ、家づくりに関して相談したい方は、ぜひ一度お近くの展示場にお越しください。
【全国のトヨタホーム展示場を探す】
https://www.toyotahome.co.jp/s/tenjijo/?ad_cd=hometag
【カタログ請求はこちら】
https://www.toyotahome.co.jp/s/catalog/?ad_cd=hometag
▼関連する記事
注文住宅とは?建売住宅との違いは?価格の相場や流れも分かりやすく解説
最大で100万円!今話題の「こどもみらい住宅支援事業」とは?分かりやすく解説!
失敗しない注文住宅の間取り!7つのポイントと決める手順のコツも紹介
注文住宅の坪単価ってどうやって計算するの?平均相場も合わせてリサーチ!
ハウスメーカーの選び方!4つのポイントを押さえるだけでぴったりの会社がわかる!
こだわるなら注文住宅?スピード重視なら建売住宅?両者の違いを分かりやすく解説!
注文住宅の相場は約3,861万円!?建築費用の内訳や建築コストを抑える方法も伝授
注文住宅の予算の決め方!適正な借入金額を把握して立ててみよう
注文住宅は広いリビングが人気!その理由とは?間取り決めの参考にしよう
【新築注文住宅】家づくりの流れを4つのステップで確認!期間の目安も
【注文住宅】完成するまでどのくらい期間がかかる?流れも合わせて解説
注文住宅でこだわりのキッチンを!後悔しない選び方を詳しく解説
注文住宅を建てる際の諸費用はどのくらいかかる?内訳や相場も解説
【新築注文住宅】内装デザインの決め方は?おしゃれになるコツを実例で解説
注文住宅の費用内訳を知りたい!総費用の平均額や各費用の目安も押さえておこう
失敗しない注文住宅づくり!よくある後悔事例からやっておくべきポイントを紹介
【注文住宅】間取りの決め方、6つの手順!人気の間取りアイデアも紹介